ライアル・ワトソンの死を知ったのは、福岡伸一の『動的平衡』(木楽舎)によってだった。これまで、福岡さんには、なんとなくその記述のスタイルにワトソンとの近親性を感じ取れるところがあったが、この本の終わりの方に彼に言及しているところが出てきて「ああやっぱり、宜(むべ)なるかな」とひとりで納得していたところ、その文脈のなかからワトソンの死を惜しむという言葉が目にはいってきたのだ。
私にとって、その遅れて届いた報せはちょっとしたショックだった。というか、ここ何年もワトソンから離れていた私にとって、「もしかして、、、」という予感があたっていたことを「すでに、、、」というかたちで遅れて知ったわけだから。
映画『クジラの島の少女』を見てワトソンの珠玉の名著『未知の贈りもの』を想起したのは、そのせいもあったのかもしれない。以来、ライアル・ワトソンをめぐってさまざまな思いが沸き立ち、記憶が20年以上前に遡行していくのを止めることができない。
むろん一介の編集者にすぎない私は、彼と特別親しく交友していたわけではないし、人生のある時期、ほんの数回短い時間を共にする機会があったに過ぎない。
しかし、少なくとも私にとっては、30歳前後のある期間、彼をひとつの参照軸にして物事にたいするある種の考えや感じ方といったものが形成されていた部分があったことは確かなのである。
「ライフ・サイエンティスト」ライアル・ワトソンとのささやかな思い出を、遅れた哀悼の私的覚書として書いておきたい。
★
そのころ、都内のホテルに来日中のワトソンさん(以下は「さん」付けを省く)を訪ねたことがある。ある月刊科学誌(日本版OMNI<オムニ>)に掲載するためのインタビューが目的だった。
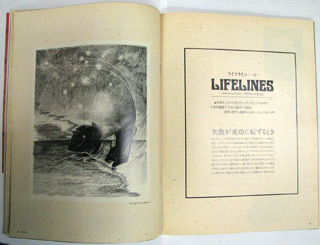 当時私は、その雑誌で日本のメディアで初となる彼の書き下ろし連載を企画し、編集に携わっていた。
当時私は、その雑誌で日本のメディアで初となる彼の書き下ろし連載を企画し、編集に携わっていた。
この連載エッセイは「ライフライン」というタイトル、内田美恵さんの日本語訳で当誌に掲載されたが、のちに旺文社から『アースワークス』という題名で単行本化された。当の昔に絶版になったが、その後ちくま文庫に入った。
挿画は、少し年上の友人として敬愛していたイラストレーターの渡辺冨士夫さんにお願いした。
渡辺さんの絵もその飄々とした人柄も大好きだった私は、渋谷のマンションの一室を作業場につかっていた彼の住まいに、打ち合せを兼ねて資料を届けたり、できあがった作品を受け取りに行くのがどんなに忙しいときでも毎回楽しみでならなかった。
その渡辺さんもこの仕事が一区切りついた後、しばらくして亡くなった。ほとんど急死といってもよいほどの、病による突然の死だった。まるで、彼が好きでよくやってみせてくれていた手品のように、私たちの目の前から一瞬にして姿を消してしまった。
(ちなみに、渡辺さんは杉浦康平さんとの仕事でブータンの切手にオファリング(供物)の絵を描いているが、この切手のセットはいまでもわが家の玄関に額装して飾ってある。)
話を戻すと、ほぼ同時期、「ライフライン」の連載前に同誌でバリ島の特集を組んだことがある。80年代前半のことだから、バリの文化について日本ではまだほとんど知られておらず、日本語のガイドブックなどまったく出ていなかった時代である。
私はそのバリ特集企画で、ワトソンに寄稿してもうことを発案した。彼ならバリを知っているだろうし好きなはずだから書いてくれるのではないかという直感が的中し、彼は一発返事で引き受けてくれた。
編集部で計画していたバリ取材に関しても、ワトソンから同行したいという意向があったが、それは出版社側の都合で不可となったため、バリでワトソンと落ち合うという私にとって夢のようなプランは実現しなかった。
ワトソンに会うのはこの東京でのインタビューがはじめてだった。
ホテルに宿泊中の彼の部屋を訪ね、握手を交わして、あなたの本のなかでは『未知の贈りもの』がいちばん好きですと述べると、あの本は自分にとっても最も愛着があり、あの本を好きだと言われるととてもうれしいと応えてくれたことを覚えている。
ちょうど『スーパーネイチュア2』が出たころのことだった(あるいは出る間近だったか)と思う。
話題は、いわゆる超常現象をめぐって、自然界の人知ではかりがたい不思議な出来事や現象、アフリカでの少年時代のことに話がおよんだ。
超常現象などというと、すぐさま「胡散臭い」という拒否反応をおこす人もあろう。だからあまりこの言葉を使いたくはないが、「常を超えた現象」と字義通りに捉えてほしいと思う。目には見えない(見えづらい)自然や生命の不思議なはたらきを認め、科学(理知)と感性(感覚知)の一体化をセンス・オブ・ワンダーの名のもとに探求したのがワトソンだったと思う(しかし、このテーマには、ここでこれ以上は触れない)。
理解する前に愛することのできる人だったと思う。
まさに驚きに満ちた話の内容もさることながら、私ははじめて会ったワトソンの偉ぶったところのかけらもない礼儀正しさと温厚な人柄、なによりその話し方に魅了された。じっとこちらを見つめるその優しいまなざしと、深いところで共振するかのようなテノールの声と。
その取材からしばらくして、OMNI(オムニ)誌でのバリ特集を発展させたかたちで、管洋志(すが・ひろし)さんの写真展『バリ 超夢幻界』が原宿ラフォーレで開かれた。その際、同時にワトソンの講演会を実施したが、会場で会うなり「イシイさん!」と呼びかけてくれて抱擁せんばかりに再会を喜んでくれた。
この写真展はOMNI(オムニ)誌でのバリ特集のさい、撮影をお願いした管さんの写真を選りすぐって作った写真集出版に合わせたものだったが、この本にはワトソン執筆による特集でのエッセイがほぼそのまま収録されている(手前味噌になるが、私は数あるバリをめぐる文章のなかでもこのエッセイが格別に好きだ)。
写真集『バリ・超夢幻界』(旺文社発行。デザインのディレクションは杉浦康平さん)は、この年の土門拳賞を受賞した。現地取材をリードしてくれた管さんの導きでバリのディープな世界を垣間見ることになった標しという意味で、そして管さんとワトソンをつないだひとつの記録という意味でも、私にとって深い愛着のある素晴らしい写真集である。いまでは入手困難なのが残念である。
また横道にそれそうだ。
さて、インタビューや講演では、ワトソンは何よりも現代における希代の語り部(ストリーテラー)であると感じた。語るように書き、書くように語れる。英語だったのでその場でどこまで理解できていたか心もとないが、あの淀みなくとうとうと語る声が、まさに大河のゆったりとした流れを思わせ、ほとんど詩の朗読でもあるかのように、彼の声を聞いているだけで心地よく、いつまでも聞きつづけていたい気持ちになったものである。
講演会のとき、質疑応答の時間があり、聴講者から「ワトソンさんのお話は素敵だけど、ロマンティストすぎるのではないか?」という問いかけがあった。それはある面、彼の読者であれば誰でもが感じることであろう。ワトソンは「自分でもある面はそうだと思っています。私は夢見ることが好きです。でも、ロマンティストであってはいけないですか?」と逆に問いを返していたことなど、なぜか本題よりはそんな細部のほうをよく憶えている。
白い馬の少年やクジラに乗った少女のように、ライアル・ワトソンも彼方の波間に姿を消してしまった(『白い馬』はアルベール・ラモリス監督のフランス映画、『クジラに乗った少女』はニキ・カーロ監督のニュージーランド映画)。
彼の死を知ったとき、「現実主義者」ばかりが幅を利かす世の中で、孤独ではあるがひとりではないといった感じに、静かに微笑む彼の後ろ姿を幻として見たのは私だけではないだろう。
★
何を起点としたとしても、記憶をたどる思考の糸はカスケード状に多数の人々や細々としたエピソードにつながり、絡み合いながら広がって、とても書き切れないという思いがしばしば書く手を止まらせる。
・・・しかし、これでもまた、長くなってしまった。
あとは、しばしの黙考に身を委ねることにしよう。
コメントを残す