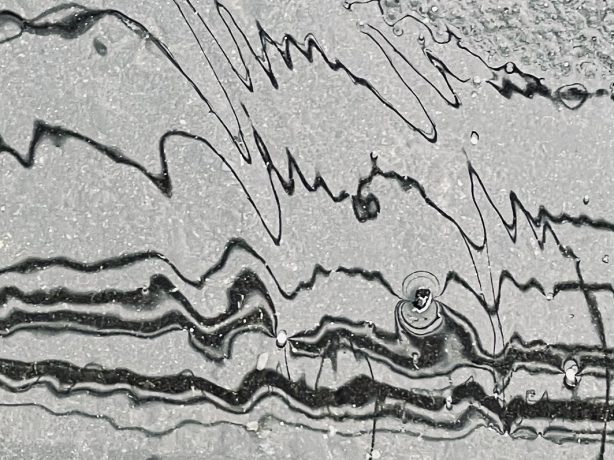
では次にいきましょう。
しかし何よりも実有<ウーシアー>であるとおもわれているのは、物体<ソーマ>である。そしてそれらの内でも自然本性的なもの<フュシコン>がそうである。なぜなら、それら自然本性的なものが、他のものの根元であるから。それらの自然本性的なものの内、一方のものは、生命<ゾーエー>を持つものであり、他方のものは生命を持っていないものである。
しかし、生命<ゾーエー>ということで我々が語っているものは、自らによる養育と成長・衰微である。従って生命に与る全ての自然本性的物体は、実有<ウーシアー>であり、結合物としての実有であろう。
それゆえ、これが生命を持ったものであり、そのような物体である以上、霊魂<プシュケー>が物体であると言うことはないであろう。事実、物体は、基体<ヒポケイメノン>に基づくもの(支えられるもの)の一つではなく基体(支えるもの)そのものであり、質料である。従って、必然的に、霊魂は、能力(可能態)として生命を持つ、自然本性的な物体の形相としての実有<ウーシアー>ということになるであろう。
この文の最後の、霊魂は「自然本性的な物体の形相としての実有<ウーシアー>ということになるであろう」という2行によって、今日、私が冒頭に言った霊魂論を巡る2つの見解、プラトン的見解と、デモクリトス的唯物論的見解の中庸をまさに自分が行くんだということをアリストテレスが宣言していると読めます。両者が合体したうえで、なおかつ霊魂は身体の形相なんだと。こういう理解が成り立つという話だけれど、その前に、実はこの前(講義4-2)の「フュシコン」。これもこれだけ読むとあとのことが全然つながってこない。
フュシコンは普通は自然的物体と訳されているが、そう訳すとギリシャ語のほんとうの意味が伝わらない。なぜならフュシコン、フュシスというのは、正に「生命のように自らを動かす根源を持つもの」というのが中心的な概念の言葉。だから最も自然本性的なものはアリストテレスにとっては生命なんです。
生命ではない石とか水とかありますが、それは地球全体の物理的な動きによって動かされているものであって、自らパワーを持って自らの欲求を持って動いているわけではない。自らの中に何らかの欲求を持って動いているものこそ本当の自然本性的なものだという理解が語られている。いかに生命が自然本性的かということだけれど、その定義はおそらく現在のウイルス学の定義と、かなり近いと同時にかなり遠い。このアリストテレスの定義は生命規定の根源を示している。要するに生命とは何かと言うと、自らによる養育と成長・衰微である。それ自体として成長と発展と衰退を繰り返すものだと。それが自ずから組み込まれているもの。そういう生命を持っているものが、本当の意味での実有である。これが生命を持ったものである。そうであれば、プシュケーは物体ではないが生命だと。
人類はいまだ生命を物体的な形で示し得たことはない。生命現象としてはさまざまな膨大なデータの堆積があっても、生命そのものを示すことはサイエンスではできない。なぜならサイエンスはサイエンスとして限界があるものだからで、それをここでアリストテレスは明確にしている。生命の根源を物体に探ろうというのは人間の思い上がった考え方、サイエンスの知性は生命を捉えることができるような能力を有していないからです。そう捉えると生命の物質的解明はまずできないのではないか。そういう自然観を持っている。だから今日の最初(講義4-1)に出てきた魂に対してわたしたちが直感的に持っている畏敬の念と、ここで深く関わってくる。
Wbさんどうですか? なにか感想はありますか。
[ Wb ] すごく抽象的な話でほとんどついていけていないのではないかと思いますが、今日の話で言えば、マルクスの限界の話があって、類的存在を量的なものとしてしか見ていないと個別性を捉えることができないという点も、アリストテレスのこういうものの理解が正確でないと我々の思考も行き詰まるのだなあと思いました。今の自然科学的な生命の捉え方が限界に突き当たるのも、その根本をたどればアリストテレスの見方への誤解があるのだなと。
それから、デジタルの話がありましたけれど、何でもかんでもデジタル化が進んでいますけど、その究極はAIなどになってくると思いますが、AIと人間存在の競合というか、いろいろ問題点が指摘されていますけれど、このように「霊魂」を考えることで、人間が人間たる独自の価値とか働きを理解することができるのではないかと思います。
まさに重要な事を2点いわれたとおもうけど、とくに後者の問題。AIと人間の生命的知能の根源はどこが違うかというと、人間の知能というのは、本来霊魂の力なので、それは生命の力なんです。生命というのは自分が成長し自己完成する志向性を持つ知性なんですよね。だから人間の知性は一定の方向性づけがされている。しかもその方向性は自らの力によって方向付けられている知性なんだということ。
ということは、逆に言うと「生きた知性」なんです。生きている知性と、死んでいる知性は根源的に違う。生きている知性は自己完成をひたすら探求しようとする完成志向態にある。AIにそれがあるか。まず根本的な、大きな規定でいったら、AIはかならず目的を外的にインプットされないと動けない知性なので、外的インプットを間違えると大変なことになる。そういう限界を認識していないといけないのに、それに対する警戒心が日本にほとんどない。それが第一点。
それから、デジタルの問題。そもそもデジタル技術による人間の情報流通は本当に生きた知性を伝達できるのかどうか。もっと根源的に考えてもらいたいところです。
さらに最初にいわれたマルクスの根源的な問題はヘーゲルの実体概念を検討せずに使ったことですね、純粋哲学的にいうと。資本論を見れば明らかなように、実体(substance)、「もの」にすぐ還元してしまっている。本当に生き生きとした実体性が彼の頭の中にはなくて、サイエンスによって捉えられる実体性に還元してしまっている。それが労働力という形になるのだろうけど、それで人間の実体性を類的なものとして把握するのは、アリストテレスへの誤解が甚だしい。だからもう一回人類の知的原点に還って考え直すべき。
[ Wb ] アリストテレスという古代の哲学者が、今のデジタル社会でも、わたしたちが今完全に見落としている部分をすごく大事なものとして取り扱っていて、だからこそ学ぶ意義もあると思います。
端的にいうと、人間の知性とは「生きている」という、生きた生命体の知性だという言葉の持つふくらみを振り返りましょうと。それに尽きると思います。
[ Wk ] ちょっといいですか。生命について僕は未知の事態、はじめての事態に対応できるもの、と考えていました。そのように言っている人もいると思う。近いのはだいぶ前にAkさんが言っていた「臨床の知」なんかの発想。どちらかというとそんなふうに考えてきた。「自らによる養育と成長・衰微」という定義は、どちらかというと外的な定義の仕方ではないかなという印象が私にはあります。
それから「完全志向態」。これは僕はいいと思う。50年くらい前、当時クローニングという技術がアメリカのUCLAなんかで生まれ始めていて、その話を耳学問で聞いたんですが、そのときに聞いたのが「細胞の全能性」。これ以前に話題になった小保方さんのスタップ細胞、クローニングはそれを使っているのですが、ニンジンの根からニンジンのすべてが生まれてくるという。人間自身も体内で幹細胞、最初の細胞から増えていって目の位置に行けば目の細胞になり、骨に行けば骨の細胞になる。細胞というのはそういう全能性を持っていて、それぞれの役割のところに行けばそういうふうになる力がある。完成志向態というのは非常にいい言葉で、かつもうちょっと複雑な意味合いも含まれてくるんじゃないかなと思います。
それから、宮崎駿の『ナウシカ』の「個は全なり」ですか。その辺の考え方も結局直接ではないけれど完成志向態というところに響き合うのではないかなと。個物の古層が全的なものをもつということはそのとおりだと思うし、たしかヘーゲルがそんなことを言っていなかったかな……。
「未知のものに対応できる」という話、もういちど言ってもらえますか。
[ Wk ] 詳しくは言えませんが、概ね生物、生命を持っているものというのは新しい環境、新しい事態で、滅びていくものもありますが、次への対応を始める個体が生まれてきて、そういう力を持っている。生命のいちばん特徴的なところは、まさにそういうところではないかなと。
いま3つの重要な論点をいわれたけど、一番最初の生命の「生成し育成し衰退する」という生命の規定が不十分だという印象を持たれたということ?
[ Wk ] あ、そうですね。
それはどういう点でそう考えたのですか。
[ Wk ] いま僕が申し上げたことが含まれていない。自分自身で自己の再生産をしていくこと。完成志向態で増えていくことだけで生命を語ったことになるのかなという疑問があります。
わたしがなにかコメントできるとすると、今のWkさんの直感は非常に重要な問題を指摘していると思う。そのうえでいうと、アリストテレスは段階的に生命というものを規定していこうとしている。後にも出てくるけど、ここで最も重要なのは生きるという原点の力、これが大事だと。そこには自己は育成し成長していくと、しかしそれは永遠のものではなく衰退すると。まずそれをいっている。さらに後に、自分と同じものを残そうとする追加的な生命の規定があって、自己と同じようなものを残そうと育成・成長・衰退を繰り返すのだということが最も重要な生命の規定だと。
意外にこれが大事なのは、人間という高度な知性体であってもそういう規定を根本的に持っているということですね。それをアリストテレスは指摘したのではないか。これがすべてではないけれども最も重要だと。
もう一つは、未知なるものへの対応力。次の段階で出てくるけれども、人間と人間以外のものを分ける最も重要な違いは、人間には知性というものがあること。そして知性の最も重要なパワーは、すべてのものを受け止める力があることだとアリストテレスは言っている。すべてのものとは未知なるものも含めて、それを受け止め理解する力があると。すべてのものと言っているので、人間知性にはなんの限定もつかないのですね。そして普遍的な力を持つ、限定のない普遍性を持つとなると彼の言い方では「神的な」、神がかったものになるということ。だから人間知性は終わりがなくて、追求すればするほど拡張し、極微化していく。そのすべてを理解できるという意味では無限な知的理解力を持つという意味が述べられていて、それがためにどうやったら生き延びられるかという対策も可能になる。
3番目の問題でいえば、スタップ細胞は失敗ですけど、これ自体は面白い。後で出てくるけど、全体と部分の関係があって、人間、生命体というのは部分と相互に入れ込んでいるといっている。あたかもトカゲのしっぽを例にとって、部分として切断されていっても切断された部分から全体を回復しようとするとする志向性が人間の生命にはある。だから人間の個々の部分と全体は相互に入り交じっていて、個の中に全体を志向するところもあるし、全体が個を志向することもある。そういう意味で全体感覚を生命体は持っているのだということろがこの後すぐ出てくる。それをこの段階でアリストテレスはかなりまとめて言っているなあと感じます。
[ Ng ] テキストがよくわかんないけど、p.2(講義4−2)の2行目か3行目、「それら自然本性的なものが、他のものの根元であるから」とあるけど、この他のものとは前に出た物体のことをいっているのか、それとも文化とか制度とか宗教とか、そういうメタなウーシアの事を言っているのか、どっちなんでしょうか。
これは、Ngさんの発言でいえば前者、物体のほうでしょうね。
[ Ng ] そうすると、自然発生的なものが他のものの根元であるから、という文章がわからない。たとえばここに人間と砂を代入すると、人間が砂の根元であるということになってしまう。
砂を動かすということではね。この世の中は2つに分かれていて、生命があるものとないものがあって、その全体が動いているのは生命があるものによって動いているのだという言い方なんだよね。
[ Ng ] なるほど。
ただ彼の説明で欠けているのは、生命のないものは生命のあるものによって動く場合もあるし、より大きな、たとえば地球が動くとか、あるいは火山がどうやって活動するか、そういう意味の説明が抜けている。それはもっと大きな意味での彼の物理学の世界があって、物理的な動と受動の関係を説明しながら、最後は神的な存在が宇宙を動かすというかなり宗教的な秩序感がある。その両建てですよね。神的な宇宙を動かす力と、生命そのものが作り出したエネルギーによって世界が回転していくという両建ての世界が彼の中にある。
[ Ng ] とにかく「他のもの」には、さきほど荒木さんが挙げた例でいえば砂のようなものを代入してもいいのですか。
砂のようなものが動く場合はね。
[ Ng ] 砂のようなものを人間が動かすと。
そう。
[ Ng ] そうすると次の行にある「他方のもの」とは砂のことですね。
その場合は人間が直接動かす場合もあるし、宇宙の物理的な力によって動くこともある。そこが抜けている。たとえば、気象学。天気予報、それを彼は独立した科学として作っていいる。雲がどうやってできて雨がどうできて風がどうして吹くのか、太陽の光がどうあたって蒸発していくのか。自然科学的な因果的な説明もしながら、では太陽のエネルギーの根源は何かと言うと、結局神の存在というところに帰着させていく。そういう世界が一方にあることも頭に入れておいてください。
では、もうちょっと行きますか。読んでみましょう。
ところで、実有<ウーシアー>は完全志向態<エンテレケイアー>である。従って、霊魂はそのような物体の完全志向態である。ただし、この完全志向態は、二重の意味を持っている。一方は知<エピステーメー>であり、他方は、観ずるということである。すると霊魂が完成志向態にあるということは、明らかに知の所持状態にあるということである。なぜなら、睡眠も覚醒も、霊魂が存在することによってはじめて可能になるからである。覚醒は観ずる働きに似ており、睡眠は、知を所持しているが、活動していない状態に似ているからである。しかし生成の観点から見れば、同一の個人において、知識の保持の方が(観よりも)先行している。従って霊魂は、力(可能態)として生命を持つ、自然本性的な物体の第一の完成志向態である。
そして、このような(自然本性的)物体とは、器官を有する<オルガニコン>物体がそれである。植物の諸々の部分も、それがまったく単純なものであっても、器官<オルガン>なのである。たとえば葉は、果実の皮を蔽うものであり、果実の皮は、果実の蔽いである。また根は、口に似ている。双方とも栄養分を吸い取るからである。それゆえにもしもすべての霊魂について何か共通であるものを語らねばならないとすれば、それは、器官というものを備えた、自然本性的な物体の、第一の完成志向態ということになるであろう。
それゆえに、霊魂と肉体が一つであるかどうかは、探求する必要がないのであって、たとえばそれは、蠟と印形が、また一般に各々の素材と、素材が担っているものとが一つであるかを探求する必要がないのと同様である。なぜなら一つであることと在ることとは様々な仕方で語られるが、その主要な意味は、ものが完成志向態である、ということなのであるから。
また抽象的なことばかりいってわかりにくいかもしれません。ここで言いたいことは要するに霊魂と身体が一つであるのか2つであるのか、長い間ギリシャ人たちも議論してきた。で、アリストテレスはその中間を行くと言ったのはどういうことかというと、蝋と印形、これが一つのものであるということを思い出してくださいと。たとえば蝋の上に印を押しますよね、それがわたしたちにとって存在しているものだというように、蝋が身体で印形が魂だということ。それが一体となって、一つのはんことして存在しているので、それは1つだと言わざるを得ない。これがバラバラであるとはいえないというのが最後の結論。
ただしその場合でも、自然的物体である肉体は魂という働きをするための器官がある。オルガニコンですね。その器官を通して肉体と霊魂が対話状態にあるという。これからアリストテレスが延々やろうとしているのは、身体と霊魂がどういうふうに競合しながら一体的な働きをしているかを事細かく分析していくことです。これが中段部分。
最初のところは、ただしその場合の霊魂の働きには2つあって、それはいつも活動するものではなく、それを蓄積している状態もある種の働きとして考えようという。蓄積していく働きは睡眠状態に近く、どんどん新しいものを取り入れようとする力は覚醒状態に近い。覚醒と睡眠が対応しながら組み合わさって霊魂というのが存在していると。
私が『ウパニシャッド』を読んでびっくりしたのは、人間が眠っていることがいかに大事かということを延々と語っている。ウパニシャッドの世界では、人間が寝ているときにこそブラフマンと一体化しているというのです。それこそ本当に開放された魂の生きた状態だと。睡眠がいかに蓄積するかということ。一見活動しているように見えないけれど睡眠が安定した蓄積状態だということがウパニシャッドに書かれている。その意味で霊魂は両方の能力をもっているのだと。
こうして、一般的な仕方において、霊魂が何であるかは語られた。すなわち言<ロゴス>の観点からいえば、実有<ウーシアー>である。すなわち実有とは、これこれの物体に対して、「在ったものとは一体何であるか」という(存在論の視角)から見たものであり、たとえば、斧のように、もし、道具的なもの<オルガン>の中の、ある種の自然本性的な物体であるようなものがあれば、それが実有である。というのは、斧であり続けたところの、或るところのもの=存在(to einai)は、斧それ自身の実有であり、それが霊魂であるから。しかし、もしこれが切り離されたならば、同名異義的に解するならばともかく、もはや斧は存在していなかったであろう。しかし今も斧は存在しているのである。
実際、霊魂とは、そのような物体の「在ったところのものは何であるか<ト・ティ・エーン・エイナイ>」、すなわち言<ロゴス>ではなく、自分自身の中に運動と静止の根元をもった、特定の、自然本性的な物体の「在ったものは何であるか<ト・ティ・エーン・エイナイ>」すなわち言<ロゴス>こそが霊魂なのである。
要するに、霊魂は宇宙になにかポコッと存在しているようなものではなく、肉体、つまり自然本性的な物体のロゴス、それが霊魂だと述べている。そういうことをここで結論づけている。結局、霊魂にアプローチするときに今までのような経験的な世界のように、わたしたちが獲得しているものの見方ではアプローチできない。霊魂にアプローチしようと思ったら、独特の存在論の視角というものがいるのだと。科学的な実験をいくら繰り返しても霊魂とは何かがわかるわけではない。どうやってわかるかというと、ものが何であるかと探求しようとするある種の洞察力がないとわからないと言っている。
例として斧の問題を出している。斧は死んでいるものだからなんの霊魂もないのだけれど、斧があたかも霊魂を持っているものだと想像してみよう。そうすると斧の霊魂というものがわかるだろうという。日本人は「道具そのものが魂を持っている」とよく感覚するけれど、それは道具に対するある種の存在論的視角だとアリストテレスはいっているわけです。もし斧の霊魂というものがあれば、その指示に従って斧は動くだろうと。それが斧の霊魂といわれるものなんだ。もしそういう霊魂がなければ、斧は単なる死んだ斧に過ぎない。そういう話ですね。––––ある程度イメージは持ってもらえるでしょうか。
[ Ak ] オルガンを器官と訳しているところと、道具的に訳しているところがありますが、どちらのイメージがより近いですか。道具というとなんとなく無機的なもの、器官というと……。
これは人間の肉体について言えば器官という訳のほうがいい。
[ Ak ] 感覚器のようなもの?
そうそう感覚器、感覚器官。外界に反応しながら人間の知性と交流する、ある種の出先機関みたいな。
[ Ak ] で、その感覚器官は単に外界に反応するだけではなく、人間が自分自身ではコントロールできない器官そのものの特性もあると。
そう。
[ Fr ] この斧のところは、日本人の感覚でいうと日本刀なんかで読み替えるといいんでしょうか。鈴木大拙の『禅と日本文化』にも、何かの刀は葉っぱを2つに切る。もう一つは葉が避けるだったかどうか忘れちゃったけど(笑)、出てきた。物体に魂があるという感覚で読むと、斧だとどうもぴったりこないけど日本刀だと納得感がある。
そういうふうに考えて、あたかも魂を持つ剣だと、そういう感覚がありますよね。それに近いですね。
[ Ng ] 「しかし今も斧は存在している」これ、どういう意味ですか。分からなくなっちゃうけど、斧に霊魂があるのかないのか。このアリストテレスの例は……。
一種の比喩ですよね。これは。行で行くと真ん中ぐらい。「もし、道具的なもの(オルガン)の中に、ある種の自然本性的な物体であるようなものがあれば」とあるでしょう。これは本当はないわけですね、斧には。それ自体のなかには。だから、あるというふうに仮定すれば、それが斧のウーシアーですよと。
[ Fr ] そういう比喩を使うということは、ないという前提で使っているのでしょうけど、当時アリストテレスの話を聞くギリシャ人にとっては、斧にも魂があるという気がしていたのではないでしょうか。
していたんでしょうね。
[ Fr ] 日本の剣豪が日本刀に魂があると感じたように。アリストテレスがそれを認めているというわけではないのでしょうけど、君たちも斧にそういうものを感じることがあるだろうと––––。
斧の比喩がすんなり受け入れらやすかった。だからおそらく生命体というのは、器官が個別的にあるのではなくて、それを全部使いこなして自己完成を遂げるウーシアーがある、そう言いたいんでしょう。
[ Ng ]「オルガン」に引っかかるんですけどね。最初の方では、植物の各部分はオルガンだと言い、で、下の斧の場合はオルガンの中の、といっているのだから、オルガンといった以上、生命があるという意味なんじゃないか。ここだけ道具的と訳してしまったら、植物の各部分はオルガンであるという主旨と矛盾する。
ここも器官的と訳したほうがいいということかな?
[ Ng ] さっき荒木さんがこだわったようにどっちかが問題なんじゃないか。
しかし、ここの文脈はどう考えても一般的な生命体の器官ではないからね。この「中の」が問題なんだけど、道具的なものの「中に」ぐらいがいいかもしれない。本来なら斧みたいな道具的なものの中にはないのだけれど、斧の中に自然本性的な物体があればという比喩、仮定。でも単に比喩なだけではなく、当時のギリシャ人にも斧が魂を持って動くと信じられていることがあったわけで、その比喩は荒唐無稽なものではないかもしれない。
まあ、これは文章上の問題もあるし、オルガンをどう訳すか、わたしも考えてみます。一応ここで言いたいことは了解ということでよろしいですか。
では、次を。
しかしながら、以上に述べられた事柄を身体の部分についても考察しなければならない。
もし目は生命体であったならば、視力はその目の霊魂というものであっただろう。なぜなら視覚は、言(ロゴス)の視点からは、眼の実有であるから。これに対して、眼は視角の素材であり、視覚が取り去られたら、それはもはや眼ではなく、石で出来た眼や描かれた眼のように、同名異義的な意味での眼でしかないのである。
さらにまた、部分において成立する事柄を、生命体の全体の体に当てはめて把握しなければならない。というのは、部分と全体との関係のように、個々の感覚全体と感覚的な身体全体 –––– それがそのようなものとして在る限り –––– との関係も、そのように類似の関係にある。ただし、霊魂が取り去られた身体は、生きることの可能なものではなく、霊魂を持つものが生きる力(可能性)を持っているのである。種子や果実は、このような力を持った物体なのである。
こうして、切断や見ることは、完全志向態としての働きであるように、覚醒していることも完全志向態である。他方で視覚や器官(オルガン=道具)の能力がそのような在り方であるのと同様に、霊魂もまた完全志向態である。しかし瞳と視覚とによって眼が成立するように、先の場合でも霊魂と身体によって生命体が成立する。
こうして、霊魂が身体から離在するものではないこと、あるいは、霊魂の一定の部分が –––– もしこの霊魂が自然本性上、部分を持つものであるとすれば ––––、離在するものではないことは明らかなことである。なぜなら霊魂の部分の中の或る部分の完成志向態は、身体の部分に属するものであるから。
しかしながら、霊魂の若干の部分については、それらが身体の如何なる部分の完成志向態でもないという理由から、それらが身体から離在することを妨げるものは何もないのである。さらに船員の船に対する関係のように、霊魂が身体の完成志向態であるのかについてはまだ明らかにされていない。
しかしともかく、霊魂については、概括的には以上のように規定され、素描されたとしよう。
いま読んだ前半部分は、霊魂と身体の関係はどういうふうに密接不可分につながっているかということを、まずは小さいところから着目して見ているわけですね。目の問題を取り上げている。目を一つの生命体と考えたら視力は目の霊魂のようなものだと。目そのものは物体としてあるわけで、全体として肉体的なもの。それを目として機能させるものは視力という一つの働きです。視覚(視力)という働きがなければいかに眼球があって角膜があって、網膜があっても見るということはできないわけです。
そういうことは、視覚、つまり目の働く力、作用というのは、眼球そのものの魂のようなもの、つまり実有のものなのだと。物体としての眼球だとかは、いわば素材であって、視覚、目の力ですね、そういったものが(目の)魂なんだと言っている。視覚という感覚的な力がなくなったら、目というものは単なる眼球にしか過ぎない。同じ目という名前で呼んでも、まったく別の働きをするものだと。これを同名意義的という言い方、それから部分と全体の問題も同じような問題があるという言い方をしている。
つまり全体がなければ部分がない。どんなに部分的な器官があったとしても、全体とのつながりがなければ器官としては働かない。だから霊魂が取り去られたとき、霊魂が生きた力を持っているのだから、生命は失われていく。だからある面で死んだように見えるような種子とか果実も、水を足せばまた発芽していくような霊魂を持ったものだと。
そうなってくると、霊魂と身体は、ある面で相即不離的な働きをしている。だから、霊魂は身体から離在するものではない。霊魂の幽体離脱とかね、死んでから生きかえって何かの働きをするとか、そういったことをアリストテレスは否定している。オカルト・ドラマでよく出てくる幽体離脱とか、霊魂はそういうものではないと。
だけれども、最後で「霊魂の若干の部分は」と彼はいう。「身体のいかなる部分の完成志向態でもない」というから、身体自身の働きがあって、それが動くことで完成される、たとえば視力、完全な働きをしようと器官を持つところは動くのだけれど、そういう身体の器官の完全(完成)志向態とはまったく別の形で霊魂の中に存在しているものがある。そういう場合は、それらが身体から離脱することを妨げるものはなにもない。つまりその部分の霊魂については、他の霊魂とは別の形で存在することもあり得る。
ここでの彼の最後のメッセージには、霊魂の離在性、霊魂の離脱ということについて、独特の表現がでてきているということに注目してほしい。この深い分析は『霊魂論』第3巻に出てきます。この霊魂と身体の相即不離、それから相即不離ではなく離在していくという、分かれて存在するということ、これをどう正しく理解するか。これがおそらくわたしたちがアリストテレスの霊魂論を理解するうえで最も大切な要だということを結論的に言って、みなさんと議論したい。Mt さん、どうですか。
[ Mt ] 先生のお話の最後の部分を取り上げますと、きっと第3巻で解説いただけると思うのですが、霊魂とは部分に分かれるんですね。「ある部分は離在しないけど、ある部分は離在する」といったら、霊魂は2つあるという感じなんでしょうか。そう受け取れますが。
そこはまた全体と部分の非常に難しいところですね。これを曲解して2つに分かれているという説もあるけど、アリストテレスにはロゴスの視点からという言葉がよく出てきますが、わかりやすく言えば概念上の区別だてにしか過ぎない。さきほどのMtさんの言葉で言えば「構成概念」なんですよ。存在としては一体。たとえばアクィナスの『神学大全』では「能力としては知性、働きとしては2つの働き」だと出ている。部分というのはどういう意味で部分と言っているのかに細心の注意を払わないと誤解します。どういう言葉がいいのか。日本語では思い浮かばないのだけど、空間的には別のものではない。
[ Mt ] もう一つ質問があります。今回の議論に関係なくて申し訳ないのですが、自分自身がぶつかっている問題があって、スピノザという人、彼はたぶんアリストテレスの影響を受けた人だと思うのですが、彼は「自然」を取り上げるときに「目的がない」ということを言っています。アリストテレスは目的があると言ってますよね。スピノザがどうしてそういう思想になったのかよくわからなくて頭悩ませているんです。
私はスピノザが専門ではないのでとんでもないことをいうかもしれないけど、おそらく西洋の知的世界を大きく取り上げると、自然も含めたすべての世界が目的論的に動かされているというのがアリストテレスの世界像であって、また大きくいえばキリスト教の世界観でもある。それに対して近代の社会は、自然と神が切断されるわけ。だからおそらくスピノザの世界観のなかに大きな知的変動があったのだろうと思います。あの当時にね。極端な場合は自然というのは完全に神の世界から離れて一種独自の独立した世界なんです。だからそれは偶然的世界でどんどん広がっていく。それが一つ。
もう一つは、スピノザがどこまで理解しているかわからないけれど、アリストテレスによると世界は究極的には神によって動いているのだけれど、ただ「偶発性」といういい方もしている。偶然的に生じてくる世界があるということもいっているのです。それを偶有性といいますね。すべては必然的な形でまわっているのだけれど、なかには偶有的な形でものが生じてくることもある。
それがなぜなのかは、わたしもまだ解明できていないけれど、たとえば有名な例でいえばミミズ。多くの場合生命から生命体ができ、それを代々繰り返していく。あるものは偶然の組み合わせによって生み出されるものもあるとアリストテレスは言っている。そういう意味なのか、自然そのものが総体として目的の連鎖という形でつながっていかないものだとスピノザが言っているのかは、わたしにはよくわからない。そこを注意して検討していっていただければいいと思います。
[ Mt ] スピノザが結局無神論ではないかという疑い、それはこの辺にあったと。
そう。だけどやっぱりスピノザは神的世界が究極において統合されていくと考えたんじゃないかな。まあ予測ですけどね。
[ Mt ] 「魂の美しさ」ということをいう人ですから、そこでつながるのかと。
[ Ng ] テキストの質問ですが、この「切断」というのは斧のことですか。「切断や見ることは完全志向態としての働きである」とある。
そうですね、斧の作用。
[ Ng ] そうすると、さっきのところを慎重に読み直す必要がありまよね。斧の完全志向態が切断であるといっている以上、斧にも魂があることになるんじゃないか。
この場合の「切断」は、人間が斧を使って切断するというだけなんじゃないのかな。
[ Ak ] この離在ということをもう少し詳しく理解したい。先生は相即不離という言葉を使われています。仏教用語ですよね。東洋人としてなんとなくわかった気持ちになってしまうのだけれど、離在と相即不離とは意味が違いますよね。離在を相即不離と理解してしまうと大きな誤解のもとになるのではないかと危惧します。離在という言葉は離れても関係があると。たとえば第1巻ででてきた「コーリトス、抽象」の関係と、身体と霊魂の関係。離在とはどっちが主でどっちが客なのか。そういう迷いが出てきます。
離在というのはもともと切り離すことができるということ。主と客ではなく、AとBを切り離すことができるというのがもともとの意味。だから身体と霊魂がもともと別のものが一体となって存在している。たとえばイメージとしては、プラトンだったらわりあい霊魂のほうが100パーセント認知能力がある。ところが身体をまとうために、それが曇らされる。だから、霊魂は身体から離れたほうが自由自在に展開できるという考え方がありますよね。アリストテレスの場合はそうではない。むしろ人間は霊魂と一体になることによって独自の霊魂の働きというものがある。それを切り離して存在することはそもそも不可能だと。
[ Ak ] 「霊魂は身体と切り離すことはできない」という言葉はすっと入ってくる。
切り離すことはできない、人間的霊魂としてはね。ただ、霊魂の働きのある部分は、身体から離れたかたちで作用する可能性があるといっている。
[ Ak ] それは「神の領域」ということですか。
そう。人間の霊魂の中には神的要素が含まれているということを、ここでちらっといっているわけです。
[ Ak ] それを「ある部分」といういい方をしている?
そうそう。ここの理解を正確にするというのが、2000年間ヨーロッパ人たちの苦しんでいることです。
皆さんに最後に申し上げたいのは、いつかどこかでまた『ニコマコス倫理学』第10巻を再読してほしいのだけれど、そこに人間のヌースの中には神的なものがあるとちゃんと書いてある。だけど人間は人間として生きている以上、そのヌースと一体となった身体の存在として追求することにしましょうという言い方ね。そういう言い方がなぜニコマコス倫理学第10巻に登場するのかということをぜひ考えてもらいたい。それはそこだけではなくて、『政治学』にも登場する。だから『政治学』と『ニコマコス倫理学』、そして『霊魂論』がいかに密接不可分につながっているのかということをここで強調しておきたいと思います。(講義4終わり)
《2021年10月30日》